公開日 2018年10月01日
更新日 2018年10月31日
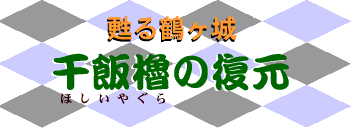
史跡若松城跡では、平成10年から平成12年にかけて干飯櫓・南走長屋の復元工事が行われました。これは、若松城天守閣再建に続く史跡若松城跡の整備であり、初めての本格的復元です。
ここでは、この復元事業に関わる様々な事柄について、当時の市政だよりで連載していた内容をお伝えします。
もくじ
- 第1回 復元工事にいたるまで
- 第2回 発掘調査
- 第3回 鶴ヶ城の写真はいつ撮影されたのか
- 第4回 石垣の積み替え
- 第5回 干飯櫓はいつ建てられたのか
- 第6回 使用木材について
- 第7回 木材加工技術
- 第8回 櫓の木構造 その1
- 第9回 櫓の木構造 その2
- 第10回 屋根の構造
- 第11回 屋根瓦
- 第12回 瓦の作成
- 第13回 瓦文様
- 第14回 瓦葺き工事
- 第15回 棟納め
- 第16回 干飯櫓・南走り長屋の利活用について
- 第17回 干飯櫓・南走長屋の役割について
- 第18回 壁下地と壁土
- 第19回 土塗り壁
- 第20回 漆喰
- 第21回 白漆喰塗り仕上げ
- 第22回 鶴ヶ城の古写真
- 第23回 幕末の鶴ヶ城の全景
- 第24回 史跡若松城跡の今後
第1回 復元工事にいたるまで
 干飯櫓の完成イメージ図です。櫓の左側の建造物が南走長屋になります。干飯櫓は鶴ヶ城にあった11の櫓のうち、一番規模の大きかったもの。兵糧の貯蔵に使われていました。
干飯櫓の完成イメージ図です。櫓の左側の建造物が南走長屋になります。干飯櫓は鶴ヶ城にあった11の櫓のうち、一番規模の大きかったもの。兵糧の貯蔵に使われていました。平成10年2月に着工した鶴ヶ城の干飯櫓と南走長屋の復元工事は、2月17日に上棟式が行われ、3月までには木材の組み上げが完了しました。現在、平成12年12月の完成に向けて順調に工事が進んでいます。
市では、この工事に先がけ、会津若松市のシンボルである鶴ヶ城全体を史跡として保存するため、また、市民一人ひとりに愛され、歴史と文化を物語る場として末永く保存整備するため、「史跡若松城跡総合整備計画」を策定しました。計画の内容は、櫓、門、撤去された石垣の復元のほか、本丸御殿など往時あった建物の配置状況を敷石などで表現する平面表示、さらには園路や案内板、公衆トイレの整備、お濠の浄化など、史跡の保存整備から運営にいたるまでの多岐にわたったものです。
この整備計画に基づいて行われる今回の復元工事は、史跡として鶴ヶ城を理解していくうえでも、大変役に立つ復元であると考えています。現在の私たちは、苔むした石垣やお濠などによって、往時の鶴ヶ城をしのぶことができます。昭和40年に天守閣が再建されて、鶴ヶ城の全体像がイメージしやすくなりました。同じように、干飯櫓と南走長屋を史実にそって復元することで、鶴ヶ城が持つ歴史的空間をより実感できるようになるはずです。
この復元を実施するにあたり、まず古絵図、古文書、取り壊し前の古写真などの資料調査と復元現場の発掘調査を行いました。その調査をもとにした各工程には、慶山石を用いた石垣の補修、伝統的な木組みによる木工事、さらには、出土品の瓦から型取りした赤瓦を用いる屋根工事、荒土壁と白漆喰塗りの左官工事など、古来の技術や工法を用いています。
この「甦る鶴ヶ城―干飯櫓の復元」では、これらの伝統的な技術やさまざまな調査で新たに分かった事実を、今回から約2年間にわたり掲載していきます。調査から完成までの記録として、価値ある連載にしていきたいと思います。
(市政だより 平成11年4月1日号掲載)
第2回 発掘調査
 平成8年9月から12月までの約4カ月間にわたり行われた発掘調査では、やじりのほか当時建物の屋根に使われていた瓦なども発掘され、復元にあたっての貴重な資料となりました。
平成8年9月から12月までの約4カ月間にわたり行われた発掘調査では、やじりのほか当時建物の屋根に使われていた瓦なども発掘され、復元にあたっての貴重な資料となりました。今回の復元では、建物の設計や工事を行う前に発掘調査を実施しました。なぜ発掘調査を行うのでしょうか。
復元は、その当時あったものを外観や内部も往時のままに、同じ材料や工法を用いて建築することが基本となります。そのため、建物の写真や設計図があれば良いのですが、残念ながら鶴ヶ城の詳細な図面は1枚もなく、遠くから眺めたような写真や絵図面が2、3枚あるだけです。
写真や絵図面では、二階建や平屋といった全体の姿、屋根や窓の形、位置などの構造までは分かりません。そのため発掘調査を行い、設計の前に正確な基礎の構造や特徴、さらに出土品から当時何に使われた建物なのかなどを調べます。
では何が分かったのでしょうか。この復元部分の石垣の最も上の石や礎石と呼ばれる柱を建てた石には、基礎の木材を置いた所を削るという特徴が見られ、それによって本来の建物の大きさや、柱や壁などの基礎材が入れられた位置を明確に確認することができました。
このほかにも、干飯櫓では南側の中央に1個の礎石が見つかり、このことから建物中央部に2本の柱を持ち、この柱は2階の天井まで立つ構造だったことが分かりました。
南走長屋は絵図面から、天守閣に続く走長屋と同様の建物であったと思われます。内部は、走長屋のほぼ中央西よりに石垣に沿って石が並べられていました。この石の上に柱が立ち、柱の西側が廊下で、東側は、石垣を削った柱の位置を組み合わせると、小部屋が3つ並んでいたと考えられます。現存するものでは、干飯櫓が岡山県高梁市の備中松山城の天守や櫓、南走長屋は大阪城の続櫓と同様の構造になっています。
また、小部屋の部分から弓矢の矢の先に付けるやじりが見つかり、武器が保存されていたと考えられました。絵図面や文献でも走長屋は武器庫とされており、文献と調査の結果がほぼ合致する結果となりました。
(市政だより 平成11年5月1日号掲載)
第3回 鶴ヶ城の写真はいつ撮影されたのか
 この写真は、イタリア・ミラノ市にあるアキーレ・ベルタレッリコレクションで所蔵していたもので、明治時代にイタリア人が横浜から持ち帰ったものです。
この写真は、イタリア・ミラノ市にあるアキーレ・ベルタレッリコレクションで所蔵していたもので、明治時代にイタリア人が横浜から持ち帰ったものです。 鶴ヶ城取り壊し前の写真は、小山弥三郎という青年写真師が撮影したというのが定説になっているが、いつ撮影されたかは定かではない。弥三郎は、スイス人貿易商でありデンマーク総領事を兼ねていたエドワード・ヴァビエと同行者のエルネスト・ヴァビエが、東北地方の養蚕視察を行った際に写真師として雇われた。この旅行にはフランス人のマラン神父が通訳として同行し、旅行記を残している。
その旅行記によると、神父は1872年(明治5年)6月22日に若松に到着し、「五階建ての城などは本当に見事な光景であったが、ちょっと見ただけで満足しなければならなかったのは、残念であった」とある。ちょっと見ただけの時間で8枚以上の写真を撮影するには時間がなさすぎる。現在のカメラとは違い、当時の湿板写真は暗室テントごと移動しなければならなかったからである。しかし、このとき神父は、一行とは遅れ別行動をとっていたのである。
このことを裏付ける資料がある。当時本丸にあった若松県庁の日誌に「明治5年5月14日快晴、丁抹国人両名城跡拝見出る」「16日快晴、丁抹国総領事官へ新潟県令よりの書状、猪苗代まで添書いたし持たせ遣わし候事、翌朝付添人より返事来る」とある。また、リヨンで出版された同行者エルネストの著作の中では、1872年6月19日に若松で「四齢期の蚕」を見たとある。当時日本はまだ旧暦を使っていたが、この年の5月14日を新暦に直すと6月19日となり、日本人とスイス人が残した文献の日付が一致することになる。また、5月16日は6月21日となるため、神父が若松に到着する6月22日の前日までヴァビエらは若松に滞在したのである。
若松県庁日誌によると、ヴァビラエらは3日間滞在しており、弥三郎が鶴ヶ城を撮影するのに十分な余裕があったことが分かる。取り壊し前の鶴ヶ城が撮影されたのは、明治5年5月14日から16日の間であると特定できそうである。
(市政だより 平成11年7月1日号掲載)
第4回 石垣の積み替え
 解体した石材は、同じ場所に積み直すため一つずつに番号を付けています。積み替え用の石材は、当時「御普請山」と呼ばれていた東山町の石山から切り出しました。
解体した石材は、同じ場所に積み直すため一つずつに番号を付けています。積み替え用の石材は、当時「御普請山」と呼ばれていた東山町の石山から切り出しました。 今回の石垣補修工事は、復元される干飯櫓・南走長屋の土台となる石垣の補修で、膨らみだしている部分の積み直しや、風化などにより破損している石の交換をする工事でした。
天守台の石垣は今から約400年前、当時の領主蒲生氏郷の時代に造られたものです。天守台の積み方は「野面積み」といい、自然石をそのまま積む方法ですが、今回工事をした石垣は天守台より約50年後の築造で、当時の工法としては新しい「布積み崩し」という積み方で積まれています。この工法の特長は、『石を加工する』ということです。石を加工する(形を整える)ことによって、石とのすき間を小さくすることができ、積みやすく強固で崩れにくくなります。また、一番の利点として、「野面積み」より石垣を高く積むことができたということです。戦いの多かったこの時代において、敵から城を守る石垣はとても重要であり、強固な石垣を造るのには画期的な方法でした。時代と共に石積みの技術も短期間に進歩していったのです。
工事で使用した補足材は、東山町の石山地区から切り出した石材を使用しました。この石は通称「慶山石」と言われ、城内の大部分がこの慶山石を使用して造られています。工事で交換した石については、「平成9年度取替」と裏に墨で書き込みをし、既存の石と区別できるようにしています。
今回の工事では、昔の土木技術の高さに感心させられました。特に、石垣上端から下端までの微妙な曲面をなす壁画や曲面にするための石一つひとつの加工、積み方、そして石垣全体のバランスがすばらしかったことです。また、解体して分かった石材の奥行きなど、さまざまな技術が美しく強固な石垣を造りだしていました。
お城の石垣も造った時代によっていろいろな積み方があります。散歩しながら違いを探してみるのも、また面白いかもしれませんね。
(市政だより 平成11年8月1日号掲載)
第5回 干飯櫓はいつ建てられたのか
 若松城下絵図屏風(大須賀清光筆)〔高瀬喜左エ門氏蔵〕。城下を南西方向から描いた鳥瞰図です。干飯櫓をはじめ西出丸の櫓なども、明治初期の写真とは屋根の向きが異なっています。
若松城下絵図屏風(大須賀清光筆)〔高瀬喜左エ門氏蔵〕。城下を南西方向から描いた鳥瞰図です。干飯櫓をはじめ西出丸の櫓なども、明治初期の写真とは屋根の向きが異なっています。 復元工事の設計図面を作成する過程の中で、解明しなければならなかったことがありました。それは、干飯櫓と南走長屋はいつごろ建てられたものかということです。このことは、復元の時代設定をいつにするかという点でとても重要なことでした。
調査した絵図面の中で、正保4年(1647年)に幕府に提出された陸奥之内会津城絵図(正保城絵図)には、復元をしようとする干飯櫓と南走長屋が描かれており、これにより、当時既に建物が存在していたことが分かります。また、この絵図では天守閣が5層で描かれいます。これは、7層であったとされる天守閣が慶長16年(1611年)の会津大地震で大きく破損し、その後、寛永16年(1639年)ごろに改修されて5層に改められたことを裏付けるものです。さらには、弘化4年(1847年)以降に書かれたとされる若松城下絵図屏風には、当時の建物がより詳細に描かれており、現在の遺構とも一致するところが多々あります。
以上の調査から、干飯櫓と南走長屋については正保4年には建っていたことになります。しかし一方、天守閣をはじめ石垣などは度々改修されていることが文献に記されており、この干飯櫓と南走長屋も例外ではなく、家世実紀には延亨元年(1744年)に、膨らんだ干飯櫓下の石垣を改修した記述があり、おのずと櫓はその直後に再建されたと推定されます。以降干飯櫓は、明治7年(1874年)に取り壊されるまで百数十年ほど存在したことになります。
ただし、絵図については抽象化して書かれている部分があり、どうしても写真に勝るものはありません。そのため設計作業に際しては、広く諸外国まで写真の所蔵を問い合わせることになりました。その結果、明治初期におけるより鮮明な写真の入手に成功し、この写真により復元の時代設定を江戸時代末期とすることとし、建築工法についても当時の工法に倣うこととした設計図面が出来上がりました。
(市政だより 平成11年9月1日号掲載)
第6回 使用木材について
 南走長屋に据えられた18センチメートル角の檜の柱と、その上に架け渡された直径約30センチメートルの松の梁です。
南走長屋に据えられた18センチメートル角の檜の柱と、その上に架け渡された直径約30センチメートルの松の梁です。 江戸時代前期は、桃山時代から続く城普請や城下町造営に従う木材需要があり、飛鳥・奈良時代や第2次世界大戦後の復興期と並ぶ木材大量消費時代であったといわれています。その影響で、城下付近の木材が枯渇する傾向にあり、森林資源の枯渇回避が幕府や各藩の政策課題となりました。
会津藩でも、官地(御林)民地を問わず、木材使用の節約伐採の抑制、または用材確保のための植林奨励などの政策がとられていたようです。例えば、慶安2年(1649年)に『会津第七木』として漆木、桑、翌檜、杉、槻、松、モチノ木を定め、無許可伐採を禁止し、さらに元文5年(1740年)には、越後国に移出していた木材のうち、杉、檜、松、姫松、槻、桐、桂、朴の8品種の出材禁止や、屋敷地の竹木伐採を取り締まり、造林を奨励していました。ほかにも、沿道沿いの「並木松」の保護や災害防止のための「保安林」、軍事目的の「風致林」の保護政策もとられていました。また、幕府や他藩も、類似の政策をとっていたようです。
そのような中、干飯櫓・南走長屋が建設されましたが、当時どのような木材が使用されていたか、文献を手がかりに、またほかの城郭を参考類例として調査を行い、復元工事に使用する木材を選定しました。木材は国産材だけを使用し、中心部の赤身の部分を使います。それは、外側の白身の部分より腐食しにくく、虫害にも強いという特徴を持っているためです。
部位ごとに説明しますと、柱には6寸角(18センチメートル)の檜、土台は7寸角(21センチメートル)の栗、梁や板には松、造作材は松や杉を用いています。特に干飯櫓には直径約50センチメートル、長さ約6.5メートルの松の梁が架かり、1尺角(30センチメートル)で長さ約7メートルの欅の通し柱2本が据えられています。
現場では、すでに軸組工事が完了していますが、赤身材で総量も423石(約118立方メートル)にも及ぶため、調達するのに大変苦労しました。
(市政だより 平成11年10月1日号掲載)
第7回 木材加工技術
 手斧は、耳かきのような形をした工具。木をたたくようにして木片を削るのに用い、その際「コンコン」と心地よい木鳴りがする。仕上がりには味わい深い削り跡が残る。
手斧は、耳かきのような形をした工具。木をたたくようにして木片を削るのに用い、その際「コンコン」と心地よい木鳴りがする。仕上がりには味わい深い削り跡が残る。 奈良・平安時代の社寺建築では、斧で切り、楔で木を縦に割り、鑿で彫り、槍鉋(やりのような形をした鉋)などで削るといった数種類の鉄製工具で木材を加工していました。その後、鎌倉・室町時代になると、木を横に切る鋸や、薄く削って平らにする台鉋などが考案され、桃山・江戸時代には、今とほとんど変わらない大工具がそろうようになります。さらにこの時代は、これらの道具を巧みに扱う大工衆が全国各地に育ってきた時代でもあり、さまざまな加工を精密にできるようになりました。特に築城などの大工事では、幾人かの棟梁を長としたチームを編成し、道具と技術を駆使しながら部分ごとに分割(割普請)して作業にあたっていたようです。
当時、若松城も同じような方法で行われ、普請に関する仕事を割りつける「割場」と称する役所などが、現在の若松女子校のあたりにあったと伝えられています。
今回の復元工事は、往時の工法を再現することとし、さらに木材は、割れや狂いを少なくするため、時間をかけ十分に自然乾燥したものを使い、柱や床などは鉋仕上げ、梁は手斧といわれる工具で樹皮などをはぎ落とし、木組みの接合部は鑿や鋸で加工しています。また大工は木材の性質を良く知り、癖を見抜き適材適所に使う技術を持っており、同じ大きさの材料であっても建物のどの位置にどう使うかを考えて加工しています。また組み立ての際に間違えることのないように墨で符号を記しました。
この符号のことを「番付け」といいますが、古くからあった方法を近世になって体系化し、全国に伝わったと考えられています。番付けには「合紋」「合番」「時香」「廻り」「組合せ」などの種類があり、東日本の城においては、組合せ番付けが比較的多かったようです。組合せ番付けは、位置を数字や文字の組合せで表す合理的な方法であり、復元工事や現在の木造建築においても採用されています。
(市政だより 平成11年11月1日号掲載)
第8回 櫓の木構造 その1
 左の写真は「土台」「石落し」の組み立て状況を写したものです。石落しは、お濠りを越えて石垣をよじ登って来る敵に対し、上から防御をするためのものです。
左の写真は「土台」「石落し」の組み立て状況を写したものです。石落しは、お濠りを越えて石垣をよじ登って来る敵に対し、上から防御をするためのものです。 戦国時代の城は、急な山に領主の館を構える山城が一般的でした。桃山・江戸時代になると、政治・経済活動に有利な平野を望む丘を利用し、天守や櫓を持つ平山城が出現しました。この城の櫓は、高い石垣の上に大規模な木造建築をするといった、それまでになった建造物であるため、技術革新も行われました。
その一つが「土台」といわれる部材の考案です。この部材は、柱の下に水平に据えて、柱からの荷重を石垣や基礎に伝え、建物の足元を強固にする働きをします。また、柱を正確な位置に立てる役割も担っています。土台がなかった時代の建物は、地面に穴を掘り、そのなかに柱を入れ込む「掘立て柱」か、礎石といわれる石の上に立柱するいずれかの方法で建てられたようです。石垣のような不規則で固い地盤には、これらの工法を用いることができないため、従来なかった土台を採用したと考えられています。
干飯櫓では、四方の外側の柱は石垣の上に位置するため土台の上に載り、また、建物のほぼ中央にある二本の通し柱は、礎石の上に据える構造になっています。なお、土台の使用は、発掘調査で確認されています。(第2回 発掘調査参照)
工事では、前述の構造に基づいて復元していますが、現行の建築基準法との整合を図り、入場者の一層の安全を確保するため、遺構をほごしたうえで、その上に土台を据える構造としています。木材の接合方法として、土台同士は端部をかぎ状に加工した「継手」といわれる方法で嵌め合わせています。また、柱と土台の接合は、柱の端部を細くして、土台の中に入れ込む「柄差し」という方法を使っています。これらの方法は、ほかの各部位の接合にも使用しています。
また、古写真で、櫓の南側の石垣より迫り出した形での「石落し」が確認されました。これは土台を使うことにより備えることができたと、考えられています。
(市政だより 平成11年12月1日号掲載)
第9回 櫓の木構造 その2
 上の写真は、干飯櫓の軸組み(骨組み)の状況写真です。柱や梁、またそのほかの部材が規則的に重なりあって荷重を分散しながら、接合部を締め固める合理的な構造になっています。
上の写真は、干飯櫓の軸組み(骨組み)の状況写真です。柱や梁、またそのほかの部材が規則的に重なりあって荷重を分散しながら、接合部を締め固める合理的な構造になっています。 干飯櫓と南走長屋は本丸の南西に位置し、昭和四十年に再建された鉄門(くろがねもん)や天守閣に連なっており、干飯櫓は若松城内に十一棟あった「隅櫓」の中で一番大きな規模を持つものと考えられています。干飯櫓の規模は一階が五間×四間、二階は一階に対し両側を半間ずつ減らして四間×三間であり、延べ面積が約百四十四平方メートルあります。また、南走長屋は幅二間半で長さが約十八間の平屋(一階)建ての建物で、延べ面積は約百六十平方メートルになります。
干飯櫓と南走長屋の外壁は、鉄砲の弾を通さないほど圧塗りの土壁で仕上げられており、敵の来襲に備えて、石垣より迫り出して造られた「石落し」や壁に小さな穴をあけて敵を銃撃するための「銃眼」などの設備を設けています。
干飯櫓は「糒」(ほしい)と呼ばれる、飯を干して乾燥させたものを貯蔵していたためその名が付いたと考えられ、文字どおり食料庫であったといわれていますが、南走長屋は武器庫として利用されていたようです。
干飯櫓では、一、二階の間に建物を一周する形で屋根が付き、最上部にも屋根を載せています。屋根には厚くて重い瓦を載せるので、全体の重量を支えるために柱や梁の寸法が太くなっていますが、中央部にある二本の通し柱から梁組み(はりぐみ)を通じて、外側の多くの柱にも荷重を分散する合理的な構造になっています。
瓦などの荷重は、屋根から梁、梁から柱へと建物を上から順に押さえつける働きをし、その重さが木の接合部をきつく締め固めています。また、「貫」(ぬき)という部材を、柱の中を横切る形で幾重にも通し、木の楔(くさび)を打ち込むことにより、建物をいっそう強固にしています。
建物の重さを構造的に利用したり、楔で締め固めをする方法は、古代建築から城郭建築にも受け継がれていたようで、当時貴重であった釘や金物を、それほど使わなくても建てることが可能でした。
(市政だより 平成12年1月1日号掲載)
第10回 屋根の構造
 上は「土居葺き」の写真です。屋根全面に、木羽板を勾配に逆らわないように幾重にも貼ったところです。懸魚は、この時点ではまだ施工されていません。
上は「土居葺き」の写真です。屋根全面に、木羽板を勾配に逆らわないように幾重にも貼ったところです。懸魚は、この時点ではまだ施工されていません。 干飯櫓の屋根形状は、最上部から両側に勾(こう)配を持たせ、その四方に庇(ひさし)屋根を回した「入母屋(いりもや)」形式になっています。この屋根の特徴として、軒先が壁より大きく張り出しており、四方の角先が緩やかに反り上がっていることがあげられます。深い軒の出は、櫓の最上部のような風雨にさらされる環境の場所であっても、土壁を護り、土が流れ出るのを防いでいます。また、四方の反り上がりは、瓦の重さに耐えるための技術であり、軒先が永い間に下がって低くなるのを防ぐためのもので、同時に視覚的な釣り合いを保つ役目もあります。このようなことから、屋根部分の木工事に関しては、復元工事を進めるなかでも高い技術を必要とする難しい仕事の一つでした。
また、干飯櫓の北面と南面の妻側の壁には「懸魚(げぎょ)」と呼ばれる装飾が施されています。模様は梅の花の形状をかたどった「梅鉢」となっています。これは古写真からのものですが、あいにく干飯櫓を直接写したものはなかったものの、城内のほかの隅櫓(すみやぐら)で鮮明に映っている古写真があることから決定されました。なお、再建された天守閣も入母屋造りの屋根となっており、妻側の壁には同じく「懸魚」が飾られていますが、こちらの模様は「蕪」(かぶら)になっています。
干飯櫓と南走長屋はともに瓦葺(ぶ)きとなりますが、瓦を葺く前に野地板の上に、手で薄く割った「木羽板」を屋根全面に重ねて貼(は)ります。これを「土居葺(どいぶ)き」といいます。木羽板は、1枚の長さが30センチメートル、厚さが2~3ミリメートルありますが、段々に幾重にも重ねて敷きつめます。土居とは土台の旧称であり、下という意味もあります。この場合は、瓦の下葺きとすることにより、瓦のすき間や破損に対して雨漏りしにくくする技法です。材料は、耐水性があり腐れに強い檜の仲間である、椹(さわら)の赤身材を使用しています。木羽板を止める釘は、短くひご状にした竹を焙煎して使用しています。竹は煎ることによって、固く締まって水に強くなるためです。
(市政だより 平成12年2月1日号掲載)
第11回 屋根瓦
 発掘調査において出土した赤瓦です。復元工事で使用する瓦は、色合い・形状・文様など、出土瓦を参考に制作しています。
発掘調査において出土した赤瓦です。復元工事で使用する瓦は、色合い・形状・文様など、出土瓦を参考に制作しています。 今から400余年ほど前、時の領主蒲生氏郷は、若松城の大改修を手がけています。「新編会津風土記」によると、その屋根瓦(がわら)を作らせるため、播磨(はりま)国(現在の兵庫県)より瓦工を呼び寄せ、小田村(現市内花見ヶ丘)で製造させました。しかし、色は黒く、品質はまだ土器に近いものであったようです。その後時代が移行しても、瓦は焼かれており、やがて氏郷時代から半世紀後の藩主保科の時代には、小田村と本郷村に分けて、両方で作られるようになりました。特に本郷では、土が良質であったことにより、この瓦製造が発展、やがて陶器が製造されるようになり、これが今日の本郷焼きとなっています。
このことは、お城がいろいろな形でさまざまな産業とかかわりを持ち、それが現在の地域産業につながっている一つの典型と言えます。
その後、黒瓦は冬の寒さに凍み割れてしまうことから改良が求められました。そこで瓦に釉薬をかけて焼き、できたものを二の丸のお濠の中に寒中30日余り浸しておいたところ、壊れなかったため、以降赤瓦として城中に届けられました。
承応2年(1653年)には、太鼓門(現在の椿坂正面)が初めて赤瓦によって葺き替えられ、その後、城内の屋根瓦は、順次赤瓦に変わっていったようです。
発掘調査を行うと、現在も城跡からは、黒瓦と施釉された赤瓦の両方が出土しますが、本丸付近では約7割、復元場所からの出土においては約9割が、赤瓦で占められています。さらに城下絵図などを見ると、江戸時代後期の絵図では、屋根が赤系統の色で描かれていることが分かります。
このようなことから、復元の時代設定である江戸時代の末期には、干飯櫓・南走長屋ともに赤瓦で葺かれていた可能性が高く、このたびの工事においては、赤瓦で復元することとなりました.。
(市政だより 平成12年3月1日号掲載)
第12回 瓦の作成
 写真は、本瓦葺きにより施工中の干飯櫓の屋根の部分です。平瓦や丸瓦などさまざまな種類の瓦を組み合わせて使用しています。
写真は、本瓦葺きにより施工中の干飯櫓の屋根の部分です。平瓦や丸瓦などさまざまな種類の瓦を組み合わせて使用しています。 復元工事における屋根の仕上げは、日本瓦本瓦葺きとなります。
瓦は、土(粘土)を固めて成形し、それに釉薬(うわぐすり)を施し焼成してでき上がります。これは、手作業と機械作業の違いはあるものの、今も昔もほぼ同じ工程で製作されています。
元来日本の瓦は、地域色の豊かな材料で、その地方風土に合わせて作られてきました。その製法や仕上がりは、生産地ごとにさまざまな特徴がありますが、若松城の瓦を焼いていたといわれる会津本郷町では、残念ながら現在瓦は焼かれていません。
そこで、瓦の復元にあたっては、発掘調査により出土した瓦の素地土の定量分析(土に含まれている物質の比率の調査)、釉薬部分の蛍光X線分析(物質にX線を照射し、発生した物質固有のスペクトル解析で含まれる微量元素の調査)をし、その特徴を調べました。そして、現在の瓦の産地である、安田瓦(新潟県)、石州瓦(島根県)、三州瓦(愛知県)、大和瓦(奈良県)などに試作を依頼して、それぞれを分析、比較したところ、土の成分については、安田瓦が当時の瓦により近いものであることが分かり、復元瓦は、安田町で焼かれることになりました。また、瓦の色を決める釉薬については、分析結果を踏まえ、配分成分の調合、濃度の調整を図りながら、何度ものし焼きを繰り返しました。このような調査、分析、試作の結果復元瓦が完成しました。
その赤瓦は、現在機械化によって生産されている、艶があり鮮やかな色の画一的な規格品の赤瓦とは違い、釉薬が窯(かま)のなかで高温で焼かれ化学変化し、さまざまな色や光沢を発しながらも、全体的には赤褐色の色を鈍く呈しています。また、焼かれる時のさまざまな条件により、瓦一枚一枚の色や艶が微妙に異なり、自然で味わい深い瓦に仕上がりました。干飯櫓・南走長屋の屋根は、17種類、約2万4千枚の赤瓦で葺かれます。
(市政だより 平成12年4月1日号掲載)
第13回 瓦文様
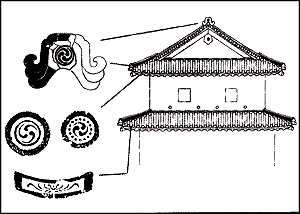 図は、干飯櫓の瓦の使用場所と出土品の瓦の拓本です。軒先の瓦には、このような文様がつけられています。
図は、干飯櫓の瓦の使用場所と出土品の瓦の拓本です。軒先の瓦には、このような文様がつけられています。 今回復元する干飯櫓と南走長屋の屋根は、発掘資料や絵図面から、瓦葺きの建物であったと考えられました。
屋根瓦のうち、屋根の上端などに付く鬼瓦と、軒の先端に付く鐙瓦(軒丸瓦)と宇瓦(軒平瓦)に文様が付けられていました。この文様は各城郭ごとに違うものになっています。復元では史実に忠実なものとの考え方から、瓦の文様についても江戸時代末期に使われていたものと同様のものにする必要があります。
古写真から瓦の文様が分かれば良いのですが、いずれの写真も小さく不鮮明なものばかりでした。このため当時を知る手段としては発掘調査の出土品が物証となります。その出土品から江戸時代末期の文様は、図のように鐙瓦は基本的に三巴文で、その周囲に珠文がめぐるものもあります。宇瓦は中心に菊花の断面状の文様が配され、その両側に唐草文が付けられています。鬼瓦は三巴文です。
日本での瓦葺きの建物は、推古天皇4年(569年)に現在の奈良県明日香村に造られた飛鳥寺が最初のものです。当時の瓦は朝鮮半島から来た人によって作られたため、文様は朝鮮半島と同じ物でした。
若松城の鐙瓦や鬼瓦に使用された巴の文様は平安時代の後期から使用され、中世以降盛んに使われるようになり、城郭や社寺建築の瓦に一般的に使用される文様となりますが、これは渦に防火の意味がこめられたためと考えられています。宇瓦の文様である菊文の意味ははっきり分かりませんが、加藤嘉明が伊予松山城から会津に入った寛永4年(1627年)以降に使われた文様と推定されます。
城郭の中では瓦の文様に家紋が使われた城もありますが、若松城跡では葵の紋がついたものは一点も見つかっていません。また、城内のいずれの櫓にも鯱(しゃち)瓦があったという明確な資料がなかったため、今回の復元で鯱瓦はつけていません。
(市政だより 平成12年5月1日号掲載)
第14回 瓦葺き工事
 写真は、土居葺きの上に平瓦を葺いている施工中のもので、瓦の下の葺土や瓦の重なった状況がわかります。
写真は、土居葺きの上に平瓦を葺いている施工中のもので、瓦の下の葺土や瓦の重なった状況がわかります。 瓦屋根の施工方法には、瓦の形状による分類と葺き方による分類があります。
まず、瓦の形状による分類には、大別して「本瓦葺き」と「桟瓦葺き」があります。本瓦葺きは、平瓦と丸瓦の組み合わせを基本に葺かれ、主に寺社、城郭などに用いられている重厚で趣のある葺き方で、飛鳥時代に朝鮮半島から伝わった葺き方です。桟瓦葺きは、平瓦と丸瓦を一体にしたような桟瓦で葺かれ、江戸時代に軽量で安価な瓦を作るために考案され、町家(民家)を中心に使われてきました。
次に、葺き方による分類には、瓦を葺く際に練土を下地の上に盛り、その上に瓦を据えて葺く「土葺工法」と、葺土を使わないで瓦を釘や緊結線で固定する「から葺工法」があります。
瓦の寸法・形状の均一性が向上した現在では、葺土を使う土葺工法は、ほとんど用いられなくなっており、桟瓦葺きを改良した「引掛桟瓦葺き」が一般に普及しています。
復元工事においては、往時の工法を再現するため、伝統的な工法である本瓦葺きの土葺工法で施工されます。実際に瓦を屋根に葺いていく方法は、土居葺き(第10回 屋根の構造参照)の上に土留桟を打ちつけ、平瓦の流れ方向に葺土(粘土にわらを混ぜ数ヶ月寝かせたもの)を筋状に盛り、平瓦を据え付けて葺き上げます。これは、瓦の座りを良くし、屋根の反りや瓦のくせなどの微妙な調整をするためのものです。
また、瓦の割り付けは、凹面上にした平瓦を半分以上重なるように葺き下ろし、その列と次の列との間に丸瓦を砂漆喰(消石灰、砂、すさ、糊などを練り合わせたもの)を用いてかぶせて葺きます。この際、瓦は3~5枚ごとに銅線で土留桟に緊結していきます。瓦の重なりが大きいため、屋根表面に見えてくる平瓦は実際の大きさの5分の1程度になっています。
このように、伝統的な工法と、職人の業により、美しい瓦屋根が葺き上がります。
(市政だより 平成12年6月1日号掲載)
第15回 棟納め
 写真は、干飯櫓の大棟の部分です。熨斗瓦積みや雁振瓦、鬼瓦などの取り付け状況がわかります。
写真は、干飯櫓の大棟の部分です。熨斗瓦積みや雁振瓦、鬼瓦などの取り付け状況がわかります。 二つの傾斜した屋根の交わる部分を棟(むね)といいます。瓦屋根の一般的な棟納めは、棟に熨斗瓦を数段積み重ね、その上に雁振瓦をかぶせて棟積みとし、その両端部に鬼瓦が据えられています。
鬼瓦は、棟の両端や隅棟、降り棟の先端に据えられる飾り瓦の総称で、瓦が日本に伝わった飛鳥時代には、蓮の花の模様が施されていました。時代とともにこの蓮華文も単純なものから複雑なものへと変化し、奈良時代になると、蓮華文と並行して獣面の模様を付けたものが作られるようになりました。平安時代には、この獣面に角の様な突起が付き、顔もより立体的になり鬼面となりました。このころから、鬼瓦と呼ばれるようになったようです。
室町時代以降になると鬼面の表情も激しくなり、下部が鰭で飾られたりして装飾化が進みます。桃山、江戸と時代に下るにしたがい、鰭などがますます発達し雲形や波形などに意匠され巨大な鬼瓦が生み出されてきました。また、一方では、城郭や町家などが発達してくると、文様も鬼面だけでなく家紋や文字を入れたり、宝珠などの富を願ったものなどが作られるようになり、鬼面のない鬼瓦も作られるようになりました。復元工事では発掘調査の出土品を参考にしていますので、鬼面のない三巴文の鬼瓦になります。
熨斗瓦は、使う位置により肌熨斗、割り熨斗などと呼ばれ、屋根の規模や瓦の葺き方により、積み重ねる熨斗瓦の段数は変わってきます。干飯櫓の棟は、雨熨斗二段、熨斗瓦を半分に割った割り熨斗を五段積みとし、上に丸瓦より少し大きめの雁振瓦をかぶせ棟積みとし、その両端に鬼瓦を据えています。
鬼瓦の作成は、鬼瓦などの彫刻的な仕事を必要とする瓦を専門に製作する鬼師と呼ばれる職人により一つひとつ手作りで作成されました。干飯櫓の屋根には、大棟に大きい瓦が二枚、二重櫓のため隅棟にひと廻り小さい鬼瓦が八枚据えられています。
(市政だより 平成12年7月1日号掲載)
第16回 干飯櫓・南走り長屋の利活用について
 写真は、左の写真は、南走長屋の銃眼です。銃を差し込む穴の大きさは直径約15センチ。このような造りは、敵の侵入を防ぐ点から必要不可欠なものでした。
写真は、左の写真は、南走長屋の銃眼です。銃を差し込む穴の大きさは直径約15センチ。このような造りは、敵の侵入を防ぐ点から必要不可欠なものでした。 今までの連載では、主に建築技法や構造、建築材料について紹介してきました。今回は少し趣向を変えて、このようにして復元される干飯櫓・南走長屋をどう利活用していくのかを紹介します。
干飯櫓・南走長屋は発掘調査や資料調査に基づいて設計され、往時の広報・技術を用いて建 てられる復元建造物です。この点が、コンクリート造りで再建した、現在の天守閣と大きく異なる特徴です。ご存知かもしれませんが、現在の天守閣は内部が郷 土博物館となっており、歴代藩主や戊辰戦争、会津漆器や本郷焼など、武家文化を中心とした会津の歴史についての資料を展示し、公開しています。
さて、干飯櫓・南走長屋についてはどのように活用していくのかということですが、前述のように、往時の工法・技術を再現した復元建造物ですので、それ自体が見る価値のあるものと言えます。つまり、往時の姿を実際に感じ取れるものであるため、 この干飯櫓・南走長屋そのものをより効果的に見せるということを主眼にして展示方法を検討しているところです。
例えば、お城の特徴的な造りとして「石落し」や「銃眼」などがあります。これらは、万が 一、城郭内に敵の侵入を許した時に撃退するために設けられたものですが、復元によって実際に目で見ることができるものです。また、せっかく往時の工法を用 いて建てられているのですから、屋根や壁の構造についても展示の中で紹介していきたいと考えています。
このように、今回の干飯櫓・南走長屋の復元によって皆さんに伝わる情報はたくさんあり、天守閣郷土博物館での展示と合わせて一体となるような展示を考え、皆さんにわかりやすく伝えられるような、また、楽しめる展示にしていきたいと考えています。
干飯櫓・南走長屋は今年の12月に竣工予定で、公開は平成13年4月をめどにしており、現在、順調に工事が進められています。
(市政だより 平成12年8月1日号掲載)
第17回 干飯櫓・南走長屋の役割について
 写真は、明治7年に取り壊される前の天守閣の写真です。砲弾を受け壁が崩れていますが、屋根瓦をしっかり支えて崩落することなく、その姿をとどめています。(所蔵:A・ベルタレッリ市立版画コレクション)
写真は、明治7年に取り壊される前の天守閣の写真です。砲弾を受け壁が崩れていますが、屋根瓦をしっかり支えて崩落することなく、その姿をとどめています。(所蔵:A・ベルタレッリ市立版画コレクション) 干飯櫓は若松城内にあった十一の二重櫓の中で一番大きかった櫓です。会津藩の文献資料である「家世実紀」では「糒櫓」とも書かれており、米を備えると書くその字のとおり、糒(干飯)などの食糧の貯蔵庫として使われていました。
この名前の元となった「干飯」は、「炒米」などとともに、当時の保存食の一つです。作り方は、案外簡単なもので、炊いたご飯を水で洗って粘りを取り、天日に干して乾燥させればできあがりです。これをそのまま食べたり、水やお湯で戻したりして食べていました。すぐに食べられるので、当時のインスタント食品といったところでしょうか。これら干飯などは、特に戦が起きたときなどは、兵士たちの食糧として重要なものでした。干飯櫓の位置が本丸の西南角にあり、鉄門、南走長屋から続いて建っているところからも、干飯は、いざというときのための蓄えであったと思われます。
また、干飯櫓は南側の濠に面しており、石落しが備えられています。このことから、お濠からの敵の侵入を防ぐ点でも、重要な役割を担っていたと思われます。
南走長屋は、表門(鉄門)から続いており、帯郭と本丸を隔てる重要な位置にあります。現在ある天守閣から表門をつなぐ走長屋とともに表門を守り、帯郭から本丸への敵の侵入を防ぐ要となっていたと思われます。
このように重要な役割を担う干飯櫓・南走長屋は、太い部材を使い丈夫な構造をしていたと考えられます。壁などは、お城のほとんどの建物に言えることですが、かなり厚く、何重にも塗られており、銃弾などが容易に貫通することができなくなっています。
天守閣の古写真を見ると、新政府軍の砲撃を受けたあとがよくわかりますが、その骨格まで全壊したわけではありません。お城の堅牢さがうかがえます。
(市政だより 平成12年9月1日号掲載)
第18回 壁下地と壁土
 外壁の小舞に工事現場で作った壁土を塗っている写真です。この工事に使用した壁土は、約80立方mとなりました。
外壁の小舞に工事現場で作った壁土を塗っている写真です。この工事に使用した壁土は、約80立方mとなりました。 復元する干飯櫓・南走長屋の壁は、「小舞(こまい)」という下地に土を塗って造る「土塗り壁」です。小舞とは、木枝などを使って格子状に編んだ塗り下地を指します。若松城の古写真の中に、土壁の破損部からのぞく竹の小舞が鮮明に写っているものがあることから、復元工事においても竹小舞を使うことにしました。竹は丈夫でまっすぐな虫の入っていないものを選び、一番身の締まった状態となる秋に刈り採った、3年ものの真竹(まだけ)を使っています。
外壁は、外からさまざまな力を受けるので、小舞も頑丈にする必要があります。直径約3センチメートルの竹をそのまま使い、太い藁縄で縦横ともに、20センチメートル間隔程度の格子状になるように組み上げます。また、部屋の間仕切壁は、直径約2センチメートルの竹を四つに割ったものを使い、細縄で網目状になるように編んで造ります。小舞は柱などに取り付け、軸組み(じゅくぐみ)(骨組み)と土壁が一体になるように施工します。
壁土は、小舞に絡みつく粘着力と、乾いたときにに固まる性質が求められることから、粘土を用います。これを壁塗り材として利用できるようにするには、細かく刻んだ藁と水を加え、かき混ぜてから寝かせます。この状態を「養生」といいますが、養生中も田畑を耕すように、何度か攪拌(かくはん)して空気を入れます。そうすることによって、藁が泥の中で徐々に発酵し分解され、土に溶けん込んでいきます。これにより、粘着力を増すばかりでなく、割れにくい壁土となります。
壁土を造るときには、藁を一度にたくさん投入したり偏って入れたりすると固まりとして残ってしまい、かえって土を損ねてしまいます。このため、適量を散布するように何度か同じことを繰り返します。さらに、藁の発酵には暑い季節が必要であり、壁土を作るためには大変な労力と長い時間を必要とします。
復元工事では、新鶴村産の粘土を用い、工事現場内で約1年半という長い時間をかけて壁土を造りました。
(市政だより 平成12年11月1日号掲載)
第19回 土塗り壁
 外壁の斑直しの写真です。縦に藁縄を入れながら、壁土で塗っている状況です。塗っている右側に下げ縄の跡が見えます。
外壁の斑直しの写真です。縦に藁縄を入れながら、壁土で塗っている状況です。塗っている右側に下げ縄の跡が見えます。 元工事の土塗り壁は、竹を藁(わら)縄で編んだ小舞に、現場で作った壁土を塗って造ります。壁土は、長い月日をかけて粘着力を持たせ、塗る前には刻んだ藁を再度混ぜ合わせます。こうすることで、施工性を良くし、塗った後で割れ落ちるのを防ぐことができます。このような効果を狙って、壁土の中に入れる藁などをすさといいます。
すさを入れた壁土は「手打ち」といって、手で団子状にしてから小舞に軽く打ちつけるように塗ります。またその裏面からも、はみ出してきたものに壁土を補って、押さえ塗りを施します。これを「裏返し」といいます。この手打ちと裏返しによって、小舞に隙間(すきま)なく壁土を塗り込めます。この作業でできた壁面は、凹凸があり、すさが出ていて荒々しい様から「荒壁打ち」と呼ばれています。
壁が塗り上がってから完全に固まるまでの数カ月間は、ひび割れが発生し続けます。このため自然な状態で養生し、乾燥したことを確認してから次の工程に移ります。この工程でひび割れをつぶすように塗り、そうすることで、仕上がったときにひび割れが生じにくくなります。
中塗りの前に、乱れた荒壁面を調整するために「鏝」を用いて壁土を何回も塗って「斑直し」を行います。斑直しに使用する壁土は、荒壁に使ったものとは違い、川砂を混ぜて使います。壁土に砂を混ぜるのは、壁土の粘土に比べて乾燥収縮が少ない砂を入れることにより、ひび割れを抑制出来るからです。また、あらかじめ小舞に縛りつけておいた「下げ縄」という藁縄を放射状に広げ、さらに縄を縦横に入れて補強しながら塗り込めることにより、壁を強化して割れを防ぎます。
中塗りは、斑直しに使ったものより砂の割合を多くした壁土を、所定の厚さまで塗り重ねます。一回に塗る厚みも、仕上がりを考慮して約5ミリ程度とし、すさは細かく刻んでから柔らかくなるまで揉みほぐした藁を使用します。
(市政だより 平成12年12月1日号掲載)
第20回 漆喰
 画像の説明等を記入(不要な場合は削除)
画像の説明等を記入(不要な場合は削除) 若松城下絵図屏風における干飯櫓・南走長屋の壁は、白く描かれています。また若松城を写した解体前の古写真などからも、壁を白漆喰で仕上げていたことが推定されています。
漆喰は主に石灰からできていますが、漆喰に使う石灰には牡蠣などの貝殻を焼いて作った「貝灰」と、石灰石を焼成して取り出した「消石灰」とがあります。
会津藩の古文書には、若松城の石灰は藩の領地であった阿賀野川流域の小川庄小花地村(現在の新潟県東蒲原郡津川町)の山中より採取した石灰石を、その村の釜で焼いてから、若松城下に送っていたと記述されています。このため復元工事にあたり同じ石灰の入手を試み、文献に記された場所の現地調査を行いました。その結果、現在では良質な石灰は取りつくされて閉山しており、同じ産地の石灰は入手できず、国内産のほかの消石灰を使うことにしました。
漆喰はこの消石灰とすさを糊の中に混ぜ併せて作ります。糊は乾燥した「角叉」という海藻を熱湯の中に入れて、形がなくなるまで煮詰めて作ります。この中には、海藻のごみやあくが浮遊しているため、きめの細かいざるでろ過したものを使います。こうしてできあがった糊の中に、あらかじめほぐしておいたすさを加え、良くなじむように竹竿で何度もかき混ぜます。漆喰に使うすさは、美しい壁を仕上げるために、※麻の繊維をさらして漂白した「晒すさ」を使います。この中に消石灰の白い粉末を練り混ぜてから、一昼夜寝かせることで漆喰ができあがります。
消石灰は、漆喰を白い化粧材にする役割を担っています。さらに、水を加えると固く結合する性質を持っていることから、接着剤の働きもしています。石灰は壁土と同じように、固まる過程で収縮を起こすことから、 を入れて強化し、ひび割れを抑制します。また、「海藻糊」には保湿作用があり、漆喰が天日に晒されても美しさと強度を保つ役割を持っています。
(市政だより 平成13年1月1日号掲載)
第21回 白漆喰塗り仕上げ
 写真は、軒の天井が波形になるように砂漆食を塗り重ねているところです。
写真は、軒の天井が波形になるように砂漆食を塗り重ねているところです。 復元する干飯櫓・南走長屋の壁は白漆喰塗り仕上げです。この仕上げは、乾燥させた土壁に「砂漆喰」という塗り材を下塗りとして施工し、その上に白漆食を塗り重ねて仕上げます。
砂漆喰とは砂と漆喰を練り合わせたもので、混ぜた砂が壁土に食い込んでから固まることで、仕上げ材が剥がれ落ちるのを防ぎます。また、白漆喰の水分が乾いた土壁に奪われないように保護し、壁土のあくが表面に滲み出てくるのを抑える役割もしています。このように砂漆喰を土壁と白漆喰の間に下塗りすることで、漆喰仕上げがいつまでもきれいに保たれるよう内側から支えているのです。
上塗りは、下塗りを施した壁面に白漆喰をこすりつけるように、薄く塗り重ねて仕上げます。白漆喰は塗ってからしばらくすると水分が表面に浮き出てきますが、これを再度鏝ずりし、壁一面を切れ目なく塗り仕上げます。白漆喰とは顔料などを混ぜない漆喰のことで純白に仕上がりますが、斑(むら)なく仕上げることによって、建物を保護しながら美しく装う、衣のような働きをしています。
若松城の古写真に写る走長屋や二重櫓の壁から大きく迫り出した軒は、波形に白く写し出されていることから、復元工事における軒の天井も白漆喰を塗って仕上げます。また、外に面した建具や窓の格子なども、白漆喰で塗り上げます。
このように、瓦を葺いた屋根以外の外部に面する部分は白漆喰で覆ってしまいます。このことを「総塗り籠め」といいます。壁や軒を塗りごめることによって火災の延焼を防ぎ、有事の際には銃弾が内部に貫通するのを防御します。また、厚く塗られた壁などは外気温を遮断し、湿度を調節する機能をあわせ持っています。
このような壁の構造や、土葺き工法により厚く施工した軒の深い瓦屋根の構造が、食料の貯蔵や武器の収納に適した室内環境を作り出していました。
(市政だより 平成13年2月1日号掲載)
第22回 鶴ヶ城の古写真
 イタリアで発見された鶴ヶ城の写真。天守閣の張出部分の白漆喰が、ほとんど崩れ落ちています
イタリアで発見された鶴ヶ城の写真。天守閣の張出部分の白漆喰が、ほとんど崩れ落ちています 今回、国内で発見された鶴ヶ城の写真。天守閣は崩れることなく保たれています
今回、国内で発見された鶴ヶ城の写真。天守閣は崩れることなく保たれています 干飯櫓・南走長屋復元事業にあたって、古写真などの資料調査を行ってきたことは以前にも述べたとおりです。この結果、イタリアでより鮮明な鶴ヶ城の古写真が発見されました。この写真は、天守閣の東面が写っているもので、今まで知られていた写真と同様のものでしたが、かなり鮮明な写真でした。
そして今回、国内で違ったアングルから撮られた鶴ヶ城の古写真が見つかりました。この写真には天守閣の南東面が写っていますが、これを従来の写真と見比べてみると、古写真の撮影にまつわる面白い事実が判明しました。
今まで、天守閣の古写真は、明治5年5月に小山弥三郎という人が撮影したというのが定説でした。ところが、2つの写真の天守閣三層の張出を比べると、従来の写真では白漆喰がほとんど崩れ落ちているのに対して、今回見つかった写真では、まだ残っている状態にあります。このことは、2枚の写真の間に時間的な経過があることを示しています。つまり、これら2枚の写真は、違う時期に撮影されたということがわかります。
国内外の様々な文献を調べてみると、小山弥三郎が撮影したのは、今回新たに見つかった天守閣南東面の写真のようです。となると、従来知られていた写真はだれが、いつ撮影したことになるのでしょうか。
これらについては、今のところ判明していません。今後の調査によって特定されるかも知れませんし、まだ見つかっていない写真が発見されるかもしれません。古写真1枚の発見で歴史の新たな一面が明らかになりました。
(市政だより 平成13年3月1日号掲載)
第23回 幕末の鶴ヶ城の全景
 完成した南走長屋の廊下です。戦いになったときなどに、兵士が走って行き来するところから「走長屋」の名が付いています。
完成した南走長屋の廊下です。戦いになったときなどに、兵士が走って行き来するところから「走長屋」の名が付いています。 今回の干飯櫓・南走長屋の復元にあたっては、建物の時代設定を幕末に設定していますが、お城は、建立当初から幕末に至るまで、時代によりその姿を変えています。
当初城地は土塁仕立てでしたが、蒲生氏郷が石垣仕立てに改修し、本丸の東側に二の丸、三の丸を構え、壮大な天守閣を築き、「鶴ケ城」と命名しました。その後、加藤明成の時代に天守閣を改修し、本丸の北と西に出丸を構築して、ほぼお城の姿が定まってきたと考えられます。残念ながら建物は、明治初期にすべて取り壊されましたが、遺構として残された石垣や土塁などから、お城がどのようなものだったかをうかがい知ることができます。
城地はお壕などで大きく区分けされますが、その分けられた区域は「郭」と呼ばれます。郭には敵の侵入を防ぐために櫓門が設けられ、櫓門までの進入路は、石垣によってかぎ形に折り曲げられ「枡形」と呼ばれる形をしていました。これは、石垣に彫られた門の跡により、容易に確認することができます。
また、郭の周囲は土塁や石垣で盛り上げられ、要所には隅櫓(すみやぐら)が建てられていました。これにより、敵の襲来をいち早く探知し、また各門に侵入してくる敵を火縄銃などで狙い撃つことができるようにし、防御力の向上を図っていたと考えられています。
鶴ケ城の隅櫓は二重櫓で、全部で11棟あったようです。干飯櫓はこれらの中でも、天守閣につながる重要な位置に建てられており、しかも、西出丸の内讃岐門(うちさぬきもん)(南側の入り口)の侵入者を狙い定めることができる位置にありました。
また走長屋は、御殿のある本丸を守るために、兵士が行き来できるよう造られた建物です。今回復元された南走長屋と天守閣再建時に建てられた走長屋のほかにも、天守閣の北側から東、また廊下橋付近まで走長屋が延びていました。上から見ると、天守閣を中心にして鳥が翼を広げたような形をしていたようです。
(市政だより 平成13年4月1日号掲載)
第24回 史跡若松城跡の今後
 再建された当時の鶴ヶ城天守閣の写真。お城は末永く残していきたいみんなの財産です
再建された当時の鶴ヶ城天守閣の写真。お城は末永く残していきたいみんなの財産です 約2年間にわたって連載してきたこのコーナーも今回が最終回です。
この連載の始めにも紹介しましたが、市では平成8年度に「史跡若松城跡総合整備計画」を策定しました。干飯櫓・南走長屋復元事業は、この計画に基づいて行われたものです。この復元事業を行うには詳細な資料調査や発掘調査が必要不可欠でした。このため、十分な資料を求めて、国内や海外の博物館などにも問い合わせました。
鶴ケ城の復元的整備の歴史をひもとくと、明治7年までに天守閣を始めとする建物がすべて取り壊され、昭和40年に天守閣を再建するまで、約90年が経過しています。この間、第2次大戦後には本丸内に競輪場が建設されるなどしました。そして天守閣の再建から平成2年に麟閣が移築復元されるまで25年、それから今回の干飯櫓・南走長屋が復元されるまでさらに10年がたっています。
ちなみに、全国的な傾向をみると昭和30年から昭和40年ごろは第1次ブームとされ、このころに再建された主なところは、名古屋城天守閣(昭和34年)、熊本城天守閣(昭和35年)などがあげられます。そして現在が第2次ブームとされ、干飯櫓・南走長屋のほかには、松本城太鼓門、駿府(すんぷ)城二之丸東御門、身近なところでは白河城などが再建されています。
いずれにしても、お城の整備を進めていくことは大変な時間と労力などを伴うことであり、史跡若松城跡の今後を考えるにあたっては長期的な展望を持つことが必要です。「城は一日にして成らず」といったところでしょうか。
天守閣や干飯櫓・南走長屋を眺めながら、往時のお城に思いをめぐらせ、そして100年後のお城を想像してみるのも一興かもしれません。
(市政だより 平成13年6月1日号掲載)
お問い合わせ
市政だよりについて
- 会津若松市役所 秘書広聴課広報広聴グループ
- 電話番号:0242-39-1206
- ファックス番号:0242-39-1402
- メール
干飯櫓・南走長屋の復元事業について
- 会津若松市役所 観光課
- 電話番号:0242-39-1251
- ファックス番号:0242-39-1433
- メール
発掘調査について
- 会津若松市役所 文化課
- 電話番号:0242-39-1305
- ファックス番号:0242-39-1272
- メール