公開日 2016年06月27日
更新日 2025年04月01日
北会津地区では、ホタルの森公園をはじめとした多くの場所にゲンジボタルがすんでいます。6月中旬から7月上旬になると幻想的な光を見ることができます。 ホタルの棲める環境づくりのためには、美しい自然、清く澄んだ流れをつくり出すことです。そのためには、まずホタルの生態を知ることが大切です。
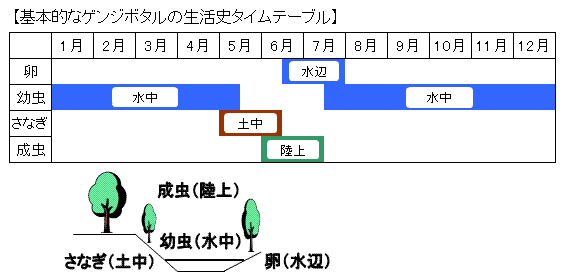
| 1月 田畑は一面の雪化粧。幼虫は、冠雪した水路の水底や石の下でじっとしています。 |
 [ゲンジボタル] 幼虫は体長25mmほど。小川でカワニナをとらえて食べる。のち、陸上の土中でさなぎになり、羽化して6月~7月頃成虫になる。成虫の体長は、オス約14mm、メス約18mmと日本で最も大きく、また親しまれているホタル。 |
| 2 月 幼虫、蛹化前の高令期に水温5℃以下の低温環境で、ひと月以下生活することが必要です。 |
|
| 3 月 日照量が多くなり、水温が上昇するにつれて、幼虫の生活行動が活発になっていきます。 |
|
| 4 月 4~5月に6令虫に成長。栄養物の摂取はこの幼虫期だけで、成虫期の生命活動と産卵活動を支えるエネルギーを貯えます。 |
 直射日光を避け、卵径約0.5mm、500個前後を産卵。羽化後3日目頃から始まり、交尾を繰返しながら数日に及ぶ |
| 5 月 中旬頃から、雨天の夜などに盛んに上陸して土まゆをつくり、さなぎ(蛹化)となります。 |
|
| 6 月 中旬からゲンジボタル、下旬にはヘイケボタルの成虫が発生し、羽化して夜空を発光飛翔します。 |
 ゲンジボタルの幼虫の成長は、ふ化時で1.5mm、脱皮するごとに令を増やし成長する |
| 7 月 6月下旬~7月上旬に、水辺の草むらに産卵した黄色の無数の卵がふ化し、その幼虫が水中に降りていきます。 |
 幼虫の生息には、夏季19℃~23℃, 冬季3℃~6℃の水温がよい、水質はよく澄んで餌が豊富なところ。ゲンジボタルの幼虫は、カワニナが好物のようだ。 |
| 8 月 ゲンジボタルの幼虫は流水中に多いカワニナ、ヘイケボタルは静水中に多いヒメタニシなどを食べて生活します。 |
|
| 9 月 7月から9月にかけて、幼虫は脱皮をくりかえしながら育ちます。始めは白くやわらかで、後黒くかたい体に。 |
 |
| 10 月 幼虫の若令期の成育適温21℃前後で、25℃を超す環境が長時間続くと発育が困難となります。 |
 6令虫で上陸することが多く、土の中で蛹化する |
| 11 月 上旬頃には、ほとんどの幼虫が4~5令虫となります。16℃以下の水温では生活行動がにぶく、発育が遅れます。 |
|
| 12 月 降雪期を迎える1月頃から水温が下がり、越冬期の幼虫の生活行動はいっそうにぶくなります。 |
 成虫の発光飛翔は第一波が午後7時 50分からその発光時間は正確で、かなり発達した時間センサーをもつ |
ゲンジボタルの生息環境づくりのために
ゲンジボタルの基本的生息条件
- 成虫
飛翔空間がある。人口照明がない。休息場所である木陰があるなど。 - 卵
水際にコケがはえている。 - 幼虫
水質が安定している。農薬や家庭排水が混入しない。カワニナが豊富にいるなど。 - さなぎ
蛹化に適した土質である。岸辺環境が物理的に長期間安定しているなど。 - その他
水温や酸素濃度などの水質的要因や下水・農薬・人工照明などの人為的要因、水辺の植物・物理的要因、生物的要因が複雑に関係しあって、ゲンジボタルの生息条件を形成しているのが大きなポイントです。
できることからはじめましょう!!
- 1年中、一定した水量を確保し流しましょう。
- 除草剤の使用量を減らしましょう。
- 減農薬・減化学肥料に取り組みましょう。
(農薬は、農地の様々な生物を死滅させ、農地から水路へ流れ出し、水が汚れる原因となります。化学肥料は、水の富栄養化を招きます。) - 4月下旬~6月(さなぎ)は上陸地の除草を控えましょう。
(ホタルが土の中でさなぎになる時期です。除草剤はホタルを死滅させます。) - 6月~7月(成虫~卵~ふ化)は草刈りを控えましょう。
(ホタルが陸上で生活する時期です。成虫は、日中は草むらで休んでいます。卵は水際のコケなどに産み付けられます。) - 下水道や浄化槽を使用しましょう。
(洗剤などの家庭雑排水は、幼虫と幼虫のエサとなるカワニナの生息を妨げます。) - 堀払いの時に、カワニナは川へ戻しましょう。
(ゲンジボタルの幼虫は、カワニナしか食べることができません。) 
お問い合わせ先
- 会津若松市役所企画政策部北会津支所まちづくり推進グループ
- 郵便番号965-0131
福島県会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11番地 - 電話:0242-58-1805(直通)
- FAX:0242-58-3500
 メール
メール